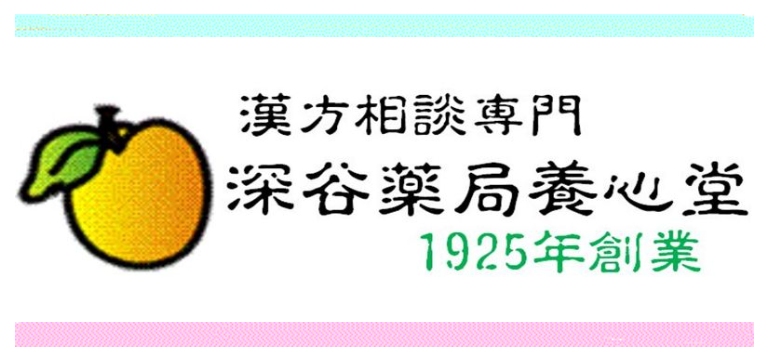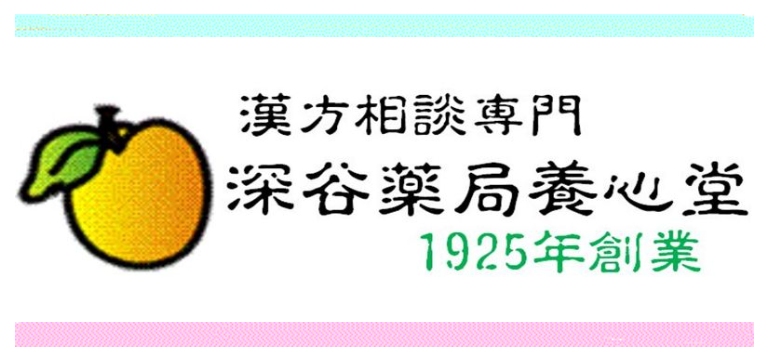目次形式に切り替える467.頑張れキネシン
最近、NHKの番組によく登場するのがキネシンだ。
キネシンは、細胞の中にあるタンパク質。
ただ、その様子は普通のタンパク質とは全く違う。
まるで生きているようなのだ。
まず、二本の足がある。
二本の足は、「えっちら」「おっちら」と、吸盤でもあるかのように物に張り付いて前に進む。
カワイイ。実にカワイイ。
NHKもこのCGはお気に入りのようで、似たような画像がよく表示されている。
二本の足の上には長いヒモがある。
ヒモの先にはまた吸盤のようなものがあり、これに物をくっつけて運んでいく。
生きているとしか思えない。
こんなものが、一つの細胞の中に無数にあって、働いているのだ。
「働く細胞」というアニメがあるが、キネシンはそれよりもさらに小さい、たった一つの細胞の中の働くタンパク質の話。
たった一つの細胞の中で、沢山の種類のタンパク質がそれぞれの役割で働いている様子はまるで小さな都市のようだ。
いくら科学が進んでも、人間はたった一つの細胞も作れない。
それもそのはず、こんなもの、作れるはずがない。
466.漢方の需要
漢方の需要は私が漢方を初めた頃と比べて随分と変わってきた。
漢方を初めた頃は、病院で治らない難しい病気の人が漢方に頼る事が多かった。
例えば重症の慢性関節リウマチ。
痛み以外にいくつかの関節が変形している事が多かった。
また、アトピー性皮膚炎。
アトピー性皮膚炎の方は今でも相談があるが、当時は今とは比較にならないくらい重症の方が多かった。
C型肝炎もとても多かった。
こういう相談は今は少なくなった。
病因の治療が進歩したというのが一番の理由だろう。
最近の漢方相談は、ストレスによる体調不良、不眠、朝起きられないなどが多い。
また、生活習慣病の改善と予防の相談も多い。
漢方が難病の治療から、予防医学の一貫にシフトしている感じがある。
確かに、病因の治療は血圧が高いなら降圧剤、コレステロールが高いならコレステロールの薬といった対症療法が多い。
これらのものも重症なら必要だけど、それ以前にやはり漢方や食事、運動などで体調管理をする事が大切だと思う。
465.中国ドラマの謎
日本のドラマはとても緻密に作られていて、見ていて矛盾を感じない。
しかし、中国のドラマはおかしな所が満載。
撮影の都合か、急に髪型がかわり、またもとに戻る。
天気もさっきまで晴れていたのに、今は雨になっている。
傘をさしているのに、人影がくっきりと。
中国のドラマはすごいスピードで撮影されて、すごいスピードで放映される。
天気なんか気にしている暇は無いのだ。
日本のドラマに比べて予算はかけているが作りはかなり雑。
でもストーリーは面白い。
細かい事は気にしない人には結構ハマると思う。
464.遺伝子解析と弁証論治
同じ薬を使っても、人により効果が出る人と出ない人がある。
違いは何だろうか?
それは生活習慣と遺伝子の違いだと思う。
実は中医学は昔から、生活習慣と遺伝子を認識していた。
遺伝子という言葉はこそ使わないが「先天の精」という概念があった。
これに生活習慣を加えて、一人ひとりの体質が出来る。
つまり先天+後天=体質となる。
同じ病気でも体質に応じて薬を使い分ける。
これを「弁証論治」と言う。
そうすると、効き目も良いし副作用も少ない。
今までの西洋医学には体質に応じてという考え方はあまり無かった。
最近になって、同じ薬を使っても効果が出る人と出ない人がいるのは何故かという事が議論されるようになって来た。
その原因として遺伝子の違いが認識されるようになって来た。
手法は違うが、西洋医学もやっと弁証論治の考え方を取り入れるようになって来たのだ。
これは非常に良い事だと思う。
弁証論治は中医学だけでなく、西洋医学にももっともっと取り入れられるべきだ。
そうすれば、投与する前から効く薬と効かない薬の区別がつく。
これこそが中医学の弁証論治の精神なのだ。
463.自己相似
図形で自己相似という概念がある。
例えば、シダ。
シダの葉っぱの一部分をちぎって拡大すると、もとのシダの形によく似ている。
一部部が全体と同じ形をしているものだ。
中医学にもちょっと似た概念がある。
例えば、耳。
耳の形は、赤ちゃんが下向きになった形に似ている。
そして、そこに色々なツボがある。
耳の中に全身のツボがあるのだ。
目も、黒目は腎、白目は肺などというように全身の縮図になっている。
舌も、手も足もそうだ。
体の一部分でありながら、全身の縮図になっている。
もっと外を見ると、人間は宇宙の縮図だと言っている。
西洋医学的にも、一つの細胞の中に染色体があり、それがなんと体そのものの縮図になっている。
このように自己相似というものが人間の体にも存在するのだ。
何と面白い事ではないか。
462.弁証論治の必要性は副作用回避
中医学の考え方に「弁証論治」がある。
証とは、体質と病状をあわせたもの。
病気の人がいた場合、その人の証を判断するのが大切という訳だ。
そして証にあわせた治療計画をたてる。
それが論治の部分だ。
弁証論治は漢方の治療効果を上げるのに不可欠なものだ。
ただ、それ以上に大切なのは副作用の回避だ。
よく漢方にも副作用があると言う人がいる。
もちろん、全く無いとは思わないが、その多くは弁証論治をしていないためだ。
漢方には潤すものと乾かすものがある。
体内の潤いが少ない津液不足や陰虚の体質の人が乾かす性質の漢方を長く続けると体内がよけいに乾燥して炎症がおこりやすくなる。
漢方の副作用に記載されている炎症系の副作用は、弁証論治せずに漢方を使った結果だと思う。
体内に余分な水分が多い体質の場合に潤いをもたせるものを長く続けるとむくみが出たり、尿量が現象する場合も考えられる。
こういった事は舌とか脈をみると判断できるのだが、弁証論治せずに、この病気ならこの漢方といった使い方をすると効き目が出ないだけでなく、色々な問題がおこる。
これを簡単に漢方の副作用と片付けてしまうのはどうかと思う。
461.無症状の弁証論治
通常は病気になるといくつかの症状が現れます。
また、舌や脈に変化が出ます。
これらの変化を中医学では四診によってとらえ、弁証論治します。
しかし、いくつかの病気は、症状がなく、舌や脈の変化も無い場合があります。
例えば、子宮漿膜下筋腫の場合とか、ごく初期のガンなどです。
これらの場合は、西洋医学の診断を使います。
例えば、子宮筋腫は、「痰瘀互結」と考えます。
この場合の瘀血は普通の瘀血と違い、陳旧瘀血と考えます。
痰も痰湿というより、頑痰と考えます。
そして、陳旧瘀血や頑痰に対する方剤を使います。
治療効果で出たかどうかは、舌や脈だけでは判断できないので、エコーやMRIの診断を参考にしていきます。
このように中医学は古い医学で診断という部分では西洋医学にかないません。
しかし、治療という方面から見ると、まだまだ利用価値がある医学です。
西洋医学の診断を活用した中医学の発展が望まれます。
460.料理と方剤
料理と処方は良く似ている。
美味しい料理は、色々な味がするが全体としては一つにまとまり、まるで良い音楽を聞いているかのように心地が良い。
すぐれた処方は、しっかりとした方向性を持っているが、それだけでなく他の方面にも気を配り、バランスよく配合している。
これを君臣佐使と言う。
君薬は主薬とも言い、その処方の方向性を決定している。
多くは処方の名前に主薬の名前が含まれている。
臣薬は、君薬を助ける。
この場合、君薬と同じ作用の場合もあるし、君薬には無い作用のものもある。
佐薬も君臣を助ける場合もあるが、多くは君薬とは違う作用のものを使い、処方独特の味付けをする。
砂糖と塩の関係のようだ。
そして、使薬は、病気の場所に薬を運ぶ。
また、全体を調和させる作用のものもある。
君薬 砂糖、臣薬 酢、佐薬 塩、使薬 胡椒
こんな感じではと思う。
ただし、処方は料理ではないので、良い処方が美味しいとは限らない。
459.常識は人によって違う
ある人が常識だと思っている事が、他の人には通用しない事がよくあります。
体質もそうです。
ある人が健康に良いと思ってやっている事が、別な人には良くない事もあります。
例えば、朝食は食べた方が良い という常識。
一般の人には当てはまりますが、脾虚の人は朝から食べられません。
消化酵素が働かないのに食事を詰め込んでも消化できないだけです。
このような人はおかゆなど消化の言いものを適量とるのが良いでしょう。
お酒の量、運動量、水の量なども個人差が大きいです。
どうしても自分のモノサシで他人を測ってしまう傾向があります。
一人一人の個性を考えて生活していく事が大切だと思います。
中医学は弁証論治といって、個人差を大切にする医学です。
同じ病気でも体質が違えば使う薬も違ってきます。
人間は機械ではありません。
機械のようにみな同じでは無いのです。
458.検査値と中医学
検査値の中で、体温、心拍数、など測定する機械がなくてもある程度解るものもあります。
ただ、多くのものが測定する機械だったり試薬が必要です。
そういった機械や試薬は中医学が出来たころにはありませんでした。
その代わりに発展していったのが舌診と脈診です。
中医学は、西洋医学のような検査結果が無くても、症状と舌診、脈診で弁証論治して体にあう処方を決める事が出来ます。
しかし、最近はどうしても検査値を重視するようになって来ました。
それで最近は中医の診断に西洋医学の検査値も取り入れられて来てはいます。
ただ、まだまだ発展途上です。
中医学の発展は西洋医学ほど急ではありません。
百年単位くらいで進歩します。
それは短所でもあり、長所でもあります。
長所というのは安全性です。
百年かけて臨床実験が行われると考えてみてください。
漢方薬はいかに安全かという事が解るでしょう。
短所は、西洋医学の検査値に中医学はまだまだ対応出来ていない事です。
例えば血圧に良い漢方、コレステロールを下げる漢方、肝機能や腎機能を改善する漢方などの需要が高まって来ています。
中医学では、これらの数値をもとに処方する方法は試行錯誤の状態です。
今、多くの中医師がどうすればこれらの数値が改善するか試行錯誤の状態です。
ただ、どんなに中医学が進んでも、検査値だけでなく体質に応じて処方する弁証論治は残っていくと思います。
次のページ トップページに戻る
トップページに戻る