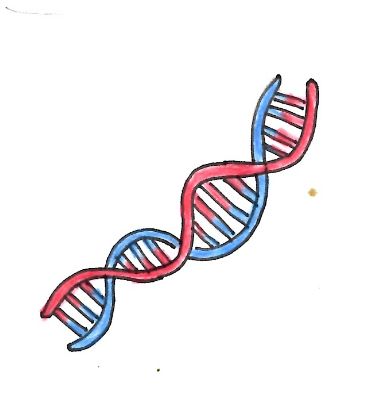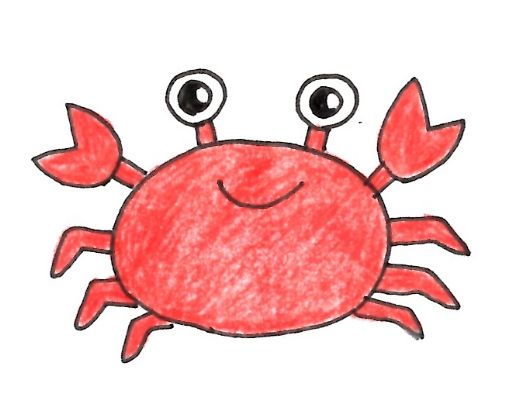目次形式に切り替える374.遺伝子
昔は、遺伝子に発生から成長までのすべての情報が書き込まれていて、それにしたがって細胞は分裂していくと考えられていた。
つまり遺伝子は生物の設計図なのだと。
しかし、遺伝子の解析が進むと、そうでは無い事がわかって来た。
人間の遺伝子は2万個ちょっとしかない。
他の下等動物と比べても殆ど差は無い。
これではとても設計図とは言えない。
遺伝子は、体に必要な材料を書いた一覧表のようなものなのだ。
では、設計図はどこにあるのだろうか?
どの遺伝子が働くか、遺伝子のスイッチを操作しているのはエピゲノムという仕組みだ。
遺伝子そのものを変化されるのではなく、スイッチを切り替えているのだ。
この切り替えがあるから、肝臓は肝臓の細胞、腎臓は腎臓の細胞というように、スイッチ切り替えるのだ。
エピゲノムは、老化や環境によって変化する。
今まで遺伝と思って諦めていたのが、実は変化する可能性があるのだ。
漢方の効果の一つとしてエピゲノムを良い方向に導く作用があるのではと思う。
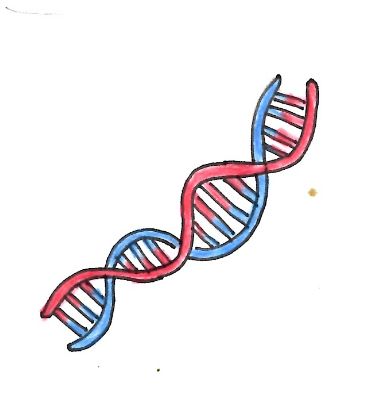
373.カニは体を冷やす?
中国人なら誰でも知っているのが、カニは体を冷やすので妊娠中は食べない方が良いという事です。
本当なのでしょうか?
個人的にカニを食べて体が冷えた感じはしません。
そこで思ったのですが、中国と日本ではカニの種類が違うのではという事です。
日本のカニは、海でとれるものです。
これに対して中国のカニは河でとれるものです。
なので性質が違うのではという事です。
ちなみにタラバガニとズワイガニでも違うのではと思うのでずか、タラバガニもズワイガニも、昔の中国にはありませんでした。
ですので、中医学的な性質は不明です。
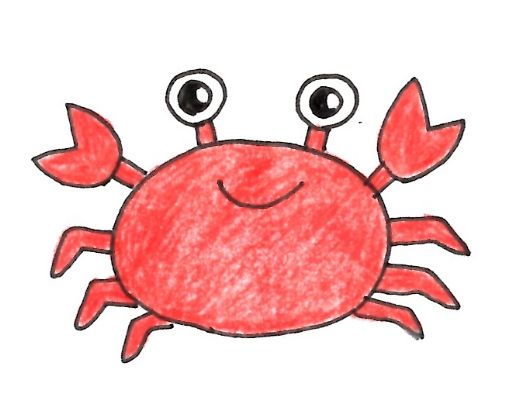
372.「あなたの体質と同じ体質のネズミはどれですか?」
そんなのわからない。
だいいち、ネズミと人間、全く違うのに、同じ体質?
こいつ、頭がおかしくなったのだろうか?
話をもどそう。
漢方は一人一人の体質や状況によって使う薬や量が違う。
これを弁証論治と言う。
経験をつんで熟練すれば、ちゃんと体にあったものを選ぶ事が出来る。
そうすれば、まず副作用は出ない。
漢方の副作用のほとんどが使い間違えだ。
エビデンスは、統計。
ネズミを使って有効率を計算する。
人間でさえ、一人一人、使う漢方が違うのに、ネズミを使って効き目を確かめる意味があるのだろうか。
漢方のエビデンス?
それは 「あなたの体質と同じ体質のネズミはこれです。ではこのネズミにこの漢方を使ってみて効き目が出ればあなたにも効くはずです。」
たしかに、ごもっとも。でも......やはり、ありえない。
漢方でエビデンスを追求する場合、どうしても漢方の基本方針からそれた使い方になる。
弁証論治しないで、みな同じ薬を使う。
ネズミにも人にも。
体質なんて考えちゃいない。
しかし、もうそれは漢方とは言えない。
効果もあまり出ないと思うし、副作用も出てくると思う。

371.防風
ある年の事です。
天候が悪くて村は大変な飢饉でした。
飢え死に寸前の村人は、仕方なくお金持ちの屋敷を襲って、食料を手にいれました。
役人が追いかけて来たので、村人たちは山奥のある古寺に隠れて、そこで暮らし始めました。
古寺は壁がくずれ落ちて、冷たいすきま風が吹いていました。
そこで、周囲に生えていた草をかり集めて壁の隙間を埋めました。
また、同じ草で布団を作ったり、煮炊き使ったりしました。
不思議な事に何ヶ月かたつと、関節炎を患っていた人たちの症状が改善して、
次々に元気になって行きました。
ある日、ある老人が息子を捜しにこの寺にやってきました。
老人は、お寺にいた息子と暮らし始めました。
この老人も関節炎で足を痛めていましたが、今までどんな事をしても治らなかった関節炎が治ってしまいました。
老人は、これは仏様が病気を治してくれたのだと思い、寺からおりて人々にこの話しを伝えました。
寺には、同じ病気で悩む人が大勢集まるようになりました。
そして、この不思議な草は、「防風」と名付けられました。

防風
産地 黒龍江、吉林など
セリ科 ボウフウの根および根茎
性味 辛・甘 微温
帰経 膀胱・肝・脾
効能 散風解表 勝湿止痛
応用 風邪、頭痛、関節痛など
370.当帰
険しい山のふもとに、一人の男が住んでいました。
山には貴重な薬草が沢山生えていました。
でも、そこには毒蛇や猛獣が沢山住んでいるので、誰も山に入ろうとはしませんでした。
ある日、この若者が勇気を振り絞って山に入る事になりました。
若者は新婚の妻に三年で帰ってくる約束をして山に向かいました。
しかし、若者は約束の三年がたっても帰って来ませんでした。
妻は、夫の身を心配するあまり、血の道の病気にかかってしまいました。
それを不憫に思った姑は、再婚を勧めました。
若者が戻ったのは、皮肉にも再婚の数日後だったのです。
事情を知った若者は、妻のもとに薬草を置いて立ち去りました。
嘆き悲しんだ妻は、死を覚悟して、薬草を手当たり次第食べてしまいました。
ところが、中毒死するどころか、反対に血の道の病気が治ってしまいました。
人々は、この薬草に当帰と名付けました。
当帰とは、「当然かえるべき」という意味です。
当然帰るぺき夫が戻らなかったので、仕方なく再婚した女性がいた事を忘れないために、
この名が付けられたと言われています。

産地 甘粛など
セリ科 北海当帰など
性味 甘・辛・苦 温
帰経 心・肝・脾
効能 補血調経 活血行血
応用 生理不順 冷え性 腹痛
めまい 便秘など
369.黄耆
ある村に、黄耆という名前の若者がいました。
若者は、貧しくて医者にかかれない人のために山から薬草を摘んできて病気を治してあげていました。
でも、若者は、お金持ちの人には親切にしませんでした。
それに腹をたてたあるお金持ちが、若者を捕まえて、役所に連れて行って牢屋に閉じこめてしまいました。
ある時、牢屋の役人の一人息子が重い病気にかかりました。
それを知った青年は薬草を与えて病気を治してあげました。
役人はとても感謝して、若者をひそかに牢屋から出してあげました。
牢屋から脱出した若者は、遠く揚子江の南まで逃げ延びて、以前のように貧しい人たちに薬草を採ってくらしました。
若者は病気を治しても、お金は受け取らず、出された食事をいただくだけだったのです。
村人は、青年に感謝して、家と薬草を耕す畑を与えました。
青年が畑で栽培した薬草はわずかでしたが、そのうちの一つは、気を補う作用があり、皮膚を引き締め
病気の進入を防ぐ作用がありました。
ある夜、残念な事にこの青年は急死してしまいまいた。
悲しんだ村人たちは、若者をしのんで彼がよく使っていた薬草に青年の名前の黄耆と名付けました。

マメ科 キバナオウギなど
産地 山西 黒龍江など
帰経 肺 脾
効能 補気升陽 益気固表
托毒生肌
応用 アレルギー
風邪ひきやすい 多汗
疲れ 脱肛など
368.貝母
ある所に、肺病にわずらっている妊婦がいました。
体が弱くて、何度妊娠しても、流産してしまうのです。
占い師などに相談しても、結果は同じでした。
家の跡継ぎを心配する姑が、嫁を実家に帰して、丈夫な赤ちゃんを産める新しい嫁を探そうとします。
それを聞いた嫁は胸をいため、悲観にくれていました。
そこへ医者が通りかかりました。
医者は「あなたは肺が悪くて、気の力も弱く、血液も足りない。
良い生薬があるから、それを飲めば丈夫な子供を産めるようになる」と言いました。
そして、ある薬草を与えました。
薬草のおかげで、嫁は元気になり、丈夫な赤ちゃんを出産しました。
喜んだ姑は医者にお礼を言いに行き、薬草の名前を尋ねました。
すると、医者は「まだ名前が無い薬草だ」と答えました。
そこで薬草に名前をつける事になりました。
生まれて来た子供には宝貝(たからものの意味)と名付けたので、
薬草の方には、母親も無事だった事から、宝貝の母、貝母と名前を付けました。

和名 アミガサユリ
産地 四川、雲南、西蔵など
味 苦、甘、微寒
帰経 肺、心
応用
咳などに杏仁、麦門冬と会わせる
肺が乾燥して、空咳が出る時は
梨と一緒に食べると良い。
367.板藍根
昔ある所に、一人の若者がいました。
若者は、あるお屋敷に住み込みで働いていました。
若者はとても働きもので、お屋敷の近くの山に、毎日、薪をとりに出かけていました。
この山には馬藍寺という寺があり、板藍和尚という老僧がすんでいました。
この老僧は、とっても親切で、お昼の時間になるといつも
若者に、白湯をふるまってあげていました。
若者も和尚の親切に感謝し、年老いた和尚のために水汲みを手伝っていました。
若者がお屋敷で働いて、しばらくたって、いつしか、若者はお屋敷の主人の娘と恋に落ちました。
しかし娘は親のいいつけで、役人に嫁がされることになってしまいました。
このことを知った板藍和尚は若者に、「死んでも生き返る」という薬を渡しました。
娘がこの薬を飲むと体が冷たくなり仮死状態になりました。
親は、娘がてっきり死んだと思い棺に入れて埋葬します。
若者は棺から娘を出し、馬藍寺に担いで行って寝かせるていると、やがて娘は息を吹き返しました。
和尚は二人のために、疫病に効くという薬草を渡しました。
二人は村を逃れ、この薬草を売って毎日幸せに暮らしました。
数年後に和尚を訪ねて見たところ、すでに和尚は亡くなっていました。
二人は和尚の恩に報いるために、和尚からもらった薬に和尚の名前をとって「板藍根」と呼ぶ事にしました。

板藍根
和名 タイセイ
産地: 江蘇、福建、広西など
味: 苦、大寒
帰経: 肺、胃
効能:清熱解毒、涼血消班
応用:
熱病が血分に入った場合。
うわごと、発疹、意識障害に
犀角、山梔子などと併せて用いる。
366.金銀花
その昔、中国に、とっても美しい双子の姉妹が住んでいました。
姉の名前は、「金花」といいました。
妹は「銀花」といいました。
ふたりはとっても仲良しでした。
ある時、姉の金花が、重い熱病にかかってしまいました。
心配した銀花は、山に薬草をとりに行きました。
しかし、金花に効く薬草はとうとう見つかりませんでした。
失意の銀花は、姉と同じ熱病にかかってしまいました。
姉妹は、当時とても流行していた熱病にかかってしまったのです。
二人の姉妹は、他の人々のために、自分たちが死んだ後、
この病気を治す薬草に生まれ変わる事を願いながら息を引き取ったのです。。
そして、二人の姉妹が亡くなったあと、姉妹を埋葬した場所の近くに、
かぐわしい金色と銀色の花をつけた植物が芽をだし、花を咲かせました。
この植物が、熱病に効く漢方薬だった事から、村人は姉妹の名前をとって、「金銀花」と名付けました。

金銀花
和名:すいかずら
産地:河南、山東など。
初夏に花蕾を取り、陰干しして用いる。
味: 甘、寒。
帰経: 肺、胃、大腸
効能: 清熱解毒 涼血、止痢
応用:
外感風熱の初期に連翹・薄荷と会わせる。
おでき、湿疹などにも用いる
365.痛みの原因
中医学では、痛みが出るのは通じないからと言います。
何が通じないかというと、気血水の流れです。
ストレスなどで気の流れが通じないと、張るような痛みが出ます。
この場合の痛みは、場所が移動するのが特徴です。
更年期の痛みとか、線維筋痛症の痛みなどに多くみられます。
気の流れを改善するような理気薬を使います。
血流が悪くなる場合は、刺すような痛みになります。
痛い場所は固定している事が多いです。
お風呂などに入り、血流をよくすると少し改善します。
活血化瘀の漢方をよく使います。
水の流れが悪い場合は、おもだるい痛みになります。
天気が悪い日に痛みがつよく、天気が良いと改善します。
水の流れを改善するような漢方を使います。
また、これ意外に冷えによるもの、筋肉、骨の弱りによるものなどもあります。
このように痛みといっても、様々な原因があり、治療法もさまざまです。
次のページ

トップページに戻る