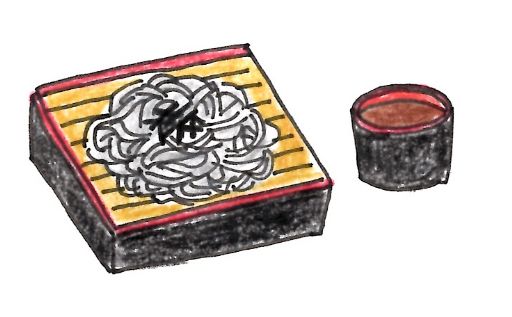目次形式に切り替える361.AIで文章を作ってみました。
中医学 春の養生法で、AIに頼んで文章を作ってもらいました。
出来上ったのが次のものです。
なかなかたいしたものです。
-------------------------------------------
タイトル: 中医学の視点で春の健康管理法を紹介します
はじめに:
春は自然界でも新しい始まりが感じられる季節です。新しい季節には、体調管理に気を使う必要があります。そこで、中医学の視点から春の健康管理法を紹介します。実践することで、健康的な生活を送りましょう。
本文:
春の気候と体の関係性:
春は気温が上昇し、自然界でも新しい命が芽吹く季節です。人間の体もこの季節に合わせて変化します。体温が上がり、新陳代謝も活発になる傾向があります。
中医学での春の特徴とは:
中医学では、春は木の気(リヴァージ)のエネルギーが最も強くなる季節と考えられています。木の気は成長力や創造力を象徴し、春にはこのエネルギーを最大限に活かすことが重要です。
春におすすめの食事や運動法:
春には体内の余分な熱を解消し、体をクールダウンさせる食材を摂ることがおすすめです。例えば、苦味のある野菜や酸味のあるフルーツ、水分が豊富な食材などが春に適しています。また、積極的な運動やストレッチも春には効果的です。
春の気に注意する病気や不調:
春には花粉症や風邪、アレルギーの症状が出やすいです。また、気温の変化や湿度の上昇により、体調不良を感じることもあります。これらの病気や不調に注意し、早めの対策を取りましょう。
中医学での春の養生法:
中医学では体のバランスを整えることが重要視されます。春には木の気のエネルギーをうまく使い、体と心を活性化させることが目指されます。適度な休息や良質な睡眠、ストレスの軽減などが大切です。
まとめ:
春は体のバランスを整えるために最適な季節です。中医学の視点から春の健康管理法を実践することで、健康的な生活を送ることができます。季節の変わり目に感じる不調や病気を防ぎ、心身の活力を高めましょう。
Note:
ぜひ、この記事を読んで、春の健康管理法を実践してみてください。あなたの健康がさらに輝くことを願っています!
360.中医学の陰と陽の概念
中国文化を知る上で八卦の概念は欠かせない。
爻と呼ばれる記号のようなものを三本かさねて八卦を作る。
爻には陽をあらわす-と、陰をあらわす- -で構成されている。
陽を三本かさねると☰で、これを乾と言って純陽をあらわす。
中医学では純粋な陽は存在しないと考える。
どんなに陽的なものであっても少しは陰が混ざるからである。
例えば火は実体がなく熱を持ち、変化するという陽の性質を全部もっている。
しかし、そんな火でもわずかに陰の性質ももっていると考えている。
それで火は☲(離)で表現している。
上と下の二本の陽が一本の陰を挟んでいる。
そうすると外見は陽だが、中に陰を含んでいる。
じつにみごとな表現だ。
陰が3つかさなった☷(坤)は陰の象徴だが、地球上で一番陰の要素をもっている水は☵(坎)で表現している。
絶対零度という概念がある。
分子の動きは温度が下がると遅くなる。
そうすると、どんどんと温度を下げると分子の動きは止まってしまう。
と、以前は考えられていた。
それを絶対零度という。
しかし、実際は絶対零度の世界でも多少の分子の振動はあるとわかっている。
つまり、完全な陰は存在しない。
水を完全な陰でなく、中に陽を含んだ☵で表現するのは素晴らしいアイディアだと思う。
アインシュタインの相対性理論では、エネルギーと物質は互いに変換される。
つまり陰と陽は、転化される。
中医学の世界でも、陰が極まると陽を生じ、陽が極まると陰を生じるとなっている。
昔の人の観察力はすごいものだと思う。
359.風熱と風寒
中医学の基本として、風熱には辛涼解表薬、風寒には辛温解表薬を使う。
辛味は、発散させる作用があるので、風熱と風寒どちらにも対応できる。
熱は冷やす必要があり涼薬、寒は温める必要があるので温薬を使う。
ただ、実際の臨床では、風熱と風寒が入り混じったような状態が良く見られる。
葛根湯や麻黄湯と銀翹解毒散をあわせて使う事が多いのだが、処方の主役は
麻黄 桂枝 銀花 連翹 の4つだ。
そこで、この4つを含む処方を検索してみると、驚く事に見当たらない。
勿論、すべての処方を検索出来る訳ではないのだが、少なくとも有名な処方にはない。
とても不思議だ。
358.台湾の漢方事情
台湾も中国と同じように、漢方薬は盛んです。
ただ、大陸の漢方と少し違います。
基本的に煎じ薬はあまり使いません。
エキス剤を中心にして、それに単味の生薬エキスをいくつか加えるという方法です。
この方法は全く自由に処方を組み立てる事は出来ないのですが、慣れてくればある程度、オリジナルの処方を作る事が出来ます。
また、煎じる手間も無いので、とても良い方法だと思います。
357.清鼻湯
台湾に行った時に鼻がつまり、あいにく手持ちの漢方薬が無かったので、台北の漢方薬のお店に入りました。
店には沢山の漢方薬が並んでいました。
その中に「清鼻湯」というのがありました。

これは日本には無いものです。
とりあえず、購入して処方を確認してみました。

日本で鼻詰まりによく使われる葛根湯加川芎辛夷に、桔梗、石膏、大黄、薏苡仁が加えられた処方でした。
鼻詰まりの初期は、葛根湯加川芎辛夷はよく効きます。
ただ、だんだんと化熱してくると、もう少し清熱のものが必要になって来ます。
石膏と大黄を入れたのはこのためと思います。
桔梗、薏苡仁は膿がたまった場合によく効きます。
なかなか良く出来た処方と思います。
必要に応じて十薬、金銀花などをいれるともっと良いかも知れません。
356.中医学の臓腑は部位でなく働き
現代医学で、肝臓とか心臓とか言うと、実体があるものです。
標本などを見た事がある人もあるでしょう。
勿論、それぞれの臓腑には機能があるのでただの物ではありません。
中医学で肺とか心というと、実体があるとも無いとも言えます。
たとえば肺は呼吸を司るので、現代医学の肺に近いものがあります。
ただ肺のはたらきとしては免疫、気の流れの調節なども含みます。
肝は血を蓄えるだけでなく自律神経の調整もしています。
心に至っては脳の働きも含めています。
不眠などは心の働きの問題です。
ですから、解剖して「これが中医学の心だよ」と言う事は出来ないのです。
中医学の「心」は体の特定の部位を指すのではなく、特定の「働き」を指すものなのです。。
355.方剤
比較的原始的な医学として、ある病気をある薬草で治すというのがある。
ゲームなどでも、体力の回復に「やくそう」という項目があったりする。
ただ、全部の病気にそれに適した薬草がある訳ではない。
それなら、1つの病気に1つの薬草という考えでは多くの病気は治せない。
そこで考え出されたのが方剤だ。
1つの病気に対して、いくつかの生薬を使って治療する。
それでも、治る場合と治らない場合がある。
どんな場合に治り、どんな場合に治らないのか?
そこで出てきたのが、弁証論治という方法だ。
1つの病気を治すのに、体質や症状に応じた処方を使おうというのだ。
例えば、風邪に使う漢方。
有名なのが葛根湯。
しかし、葛根湯で治る風邪と治らない風邪がある。
葛根湯以外でよく使うのが
銀翹解毒散 荊防排毒散 小青龍湯 麻杏甘石湯 藿香正気散 参蘇飲 香蘇散
などだ。
同じ病気でも、違う漢方を使う。
これを同病異治という。
354.「かけそば」と「ざるそば」
かけそばとざるそばでは、タレが少し違います。
ざるそばは、鰹節をメインにしたパンチがあるタレです。
それに対してかけそばは、みりんを少し多めにして、しいたけや他のダシも入れます。
そうめんのタレと似ています。
とても気に入っているそばつゆがあるのですが、これはざるそば用で、かけそばにしてもあまり美味しくありません。
かと言って寒い時期にはざるそばはあまり食べたくありません。
そこで、温かいざるそばを食べています。
茹でたそばを湯切りして丼に入れ、温めたざるそばのつゆをかけます。
愛用のそばつゆは、ストレートタイプなので、そのまま少量です。
お好みで卵、とろろ、ネギ、のりを入れます。
ゆず唐辛子をかけて完成です。
普通のかけそば急いで食べないとすぐに伸びてしまうのですが、これは伸びにくく最後まで美味しく食べられます。
またタレが少ないので塩分の節約にもなります。
勿論、お気に入りのタレとのマッチングも最高です。
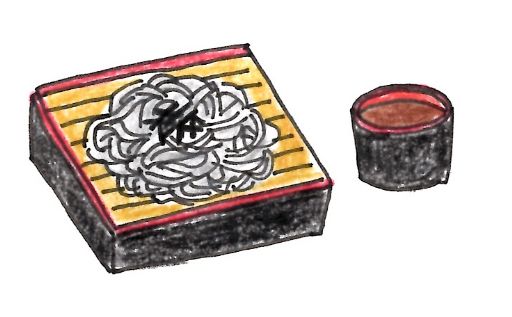
353.刈谷のクーポン
ラインに刈谷市登録すると刈谷の特定のお店で使えるクーポンが取得できました。
当店は登録していないので使えなかったのですが、使えるお店はかなり賑わっていました。
毎週2000円ずつ、6週間、合計金額で12000円分のクーポンが使えるというなかなかの大判振る舞いでした。
クーポンが使えるのは刈谷市民だけでなくて、誰でも大丈夫。
という事で、あっという間に終了。
6週間が2週間で終わってしまいました。
3週間目も、少量発行するという事でしたが、取得するのがとても困難でした。
352.中医学の勉強をすすめるための4つのステップ
ステップ1 基礎づくり
中医学基礎、内科学、婦科学、方剤学、中薬学の教科書を読む
この部分は、店頭で役立たない事も多いが中医学を理解するためには必要なので頑張る。
完全に記憶しなくても、後で忘れても良いと思う。
細かい事を完全に記憶するより、中医学全体の構造を把握するの事が大切。
ステップ2 臨床を学ぶ
臨床実践をマスターするためには医案を読むのが良い。
ただ、古い医案はだめ。1960年以降のものが良い。
何故かというと、古い医案には西洋医学の診断が無い。
例えば同じ「胃痛」でも、胃痙攣、胃潰瘍、慢性胃炎、胃がんなどがあり、簡単に「胃痛」ではくくれない。
病名が胃痛となっている医案はあまり参考にならない。
これらの医案は日本語に翻訳されていないものが多い。
なので、中国語で読む必要がある。
これらの医案は読むだけなら中国語でもそんなに難しくない。
簡体字を100程度覚えれば何とかなる。
発音は出来なくても、漢文を読む要領で良いと思う。
ステップ3 古典を学ぶ
中医学を深く理解するには古典を読む事が必要。
古典を学ぶと、中医学の発展の歴史がわかり、どのように変化して来たか分かる。
また単なる医療ではなく中国の文化や哲学と深く結びついているのが分かる。
古典は海のように広く、おそらく一生かかっても学び切れない。
古典の世界に浸っていると、ミイラ取りがミイラになる。
なので、適当に切り上げる方がおすすめ。
勿論、古典が好きなら一生勉強するのも良いと思う。
ただ、店頭の漢方相談を中心にするなら古典はある程度でやめておこう。
ステップ4 新しい理論を作る
中医学は、臨床経験から、仮説を作る。
仮説は、実験をしなくても頭の中で考える事が出来る。
色々な仮説を考えてみる事は大切だと思う。
使えない仮説も沢山あるだろう。
もしその仮説が臨床に応用出来ると、時間をかけてそれは定説となる。
定説があつまり理論を作る。
中医学は一歩進んだ事になる。
伝染病の治療として、傷寒論の世界から、新しい温病の理論がるまで千年以上を要した。
これは、恐らく傷寒論があまりにも完成されたものだったので、それを継承する事しか出来ず、新しい仮説を考えなかったからだろうと思う。
次のページ

トップページに戻る