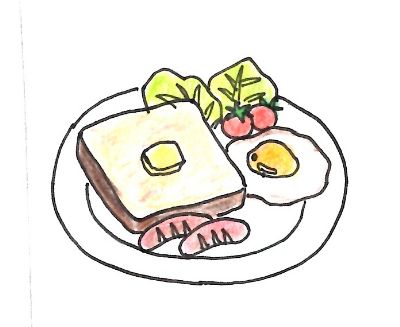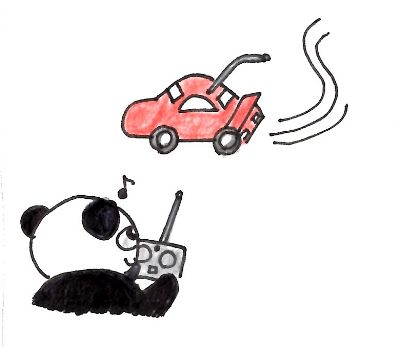目次形式に切り替える384.中医学にエビデンスは必要か?
中医学はエビデンスが無いとよく言われます。
しかし、エビデンスはそんなに大切なものでしょうか?
西洋医学は科学ですから、客観性、有効性、作用機序など科学的な目が大切です。
しかし、中医学は科学ではありません。
お医者さんが、目で観て、話を効いて、舌を見て、脈を見て、患者さんの状態を把握します。
機械は使いません。
五感だけが頼りです。

中医学で直感はとても大切です。
老中医と、若い中医師との違いは、この直感です。
直感は経験から生まれます。
20年、30年、臨床を経験すると、いくつかのバターンが見えてきます。
これが直感です。
直感は数字で表す事は難しく、そのためエビデンスにはなりません。
しかし、それはとても大切なものです。
中医学を科学化してしまい、直感よりもエビデンスを重視すると、大切な中医学の心を失う事になるでしょう。
383.診断と治療
西洋医学は治療の前にまず病名を診断します。
そしてその診断にそった治療をします。
病名が決まらないと、本格的な治療は出来ません。
中医学は、西洋医学で診断された病名は参考にはしますが、それで治療方針が決まる訳てはありせん。
あくまで参考ですから、無くても問題ありません。
中医学は二千年も前に誕生した医学で、血液検査もレントゲンもありません。
血圧計や体温計ですら無い時代です。
細菌やウイルスも発見されていませんでした。
ですから、西洋医学的な病名をつけるのは困難でした。
ではどのように考えるかというと、症状、体質、脈、舌を総合的に考えて治療します。
治療方針を「証」という-ですが、それに従って治療します。
これを弁証論治と言っています。
西洋医学的な病名が違っても証が同じなら、同じように治療します。
同じ病名でも、証が違えば治療は違います。
今の日本の大学や病院はすべて西洋医学なので、どうしても中医学を西洋医学的に考えてしまう事が多いと思います。
しかし、もともと違うものなので、混同しないようにした方が良いでしょう。
382.汗かき対策
汗がダラダラ出て止まらない。
対策として、エアコンを低めに設定している。
こんな人も多いと思う。
ただ、エアコンを低めにすると、外との温度差が大きくなり、外に出た時に汗が大量に吹き出す事になる。
汗は、体にとって必要だ。
なので、止めない方が良い。
では、どうすれば良いのだろうか?
一気に大量に汗が出るのではなく、常時少しずつ汗が出るようにする。
それにはエアコンの温度を高めにする。
そのかわり、扇風機などで風をつくる。
顔に風が来ると不快なら、手とか足に風が来るようにすると良い。
卓上の小さい扇風機で十分。
机の下などに小さい扇風機を置くとか、ハンディファンでも良い。
汗を乾かすようにする。
そうすると汗が出ても不快ではない。

381.朝食は食べる方が良いか?
テレビなどの健康番組では、必ず朝食はとるようにという指導が多い。
勿論、食べられるなら食べた方が良い。
例えば、お腹は空いているが、忙しくて食べる時間が無いなどの場合は、やはりくふうして食べるようにした方が良い
ただ、朝は食欲が出ないという人もいる。
体質は人それぞれ。
脾虚の体質の場合、朝は食欲が無い場合が多い。
食欲があるのに、時間がなくて朝食を食べないのと、食欲が無くて食べないのでは意味が全く違う。
食欲が無い場合は無理しないで、消化の良いものを食べると良い。
朝はおかゆ、というのも良い方法だ。
中国でも、朝はお粥という場合は多い。
お粥も食べたくないなら、無理には食べなくても良いと思う。
それよりも、脾虚の人はもっと気おつける事が沢山ある。
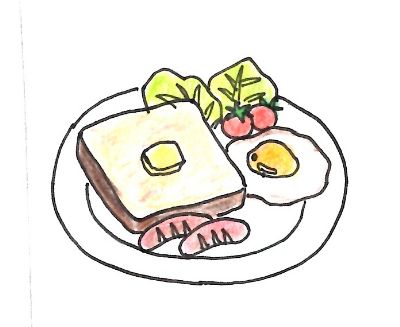
一人ひとりの体質は違うので、十把一絡げに考えるのではなく、その人の体質にあった食生活、ライフスタイルを続ける事が大切だ。
中医学は弁証論治といって、体質や状態を考え、自分の体質にあった方法を選択する事が大切だ。
380.方剤の組み合わせ
簡単な病気や症状なら一つの方剤だけで治療できる。
だが、複雑な状態だといくつかの方剤を組み合わせて使う必要がある。
中国では、処方を加減して使う事が多いが、日本では法律やさまざまな問題から一つの処方を加減して使うのは難しい。
それに代わる方法としては、いくつかの処方の組み合わせがある。
中国は、使う生薬の量がとても多い。
しかし、日本の場合は、一つの処方に含まれている生薬の量は中国よりずっと少ない。
なので、いくつかの処方を組み合わせるのは、合理的だ。
いくつかの処方をあわせる場合、バランスが大切だ。
例えばラジコンカーを運転する場合、アクセル、ブレーキ、ハンドル、バックなどの操作が必要だ。
それと同じで、アクセルにあたる処方、ハンドルにあたる処方、ブレーキにあたる処方など、組み合わせて使う。
そして、治療という目的にあった方向に誘導していくのだ。
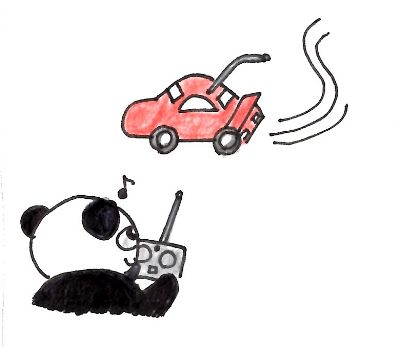
379.体に熱がこもったら
体内に熱がこもる原因は、風邪や感染症以外でもよくあります。
顔が赤い
たいして暑くないのに汗が吹き出して来る
喉が乾いて、冷たい飲み物が飲みたい
舌の色が赤い
尿の色が黄色い
便秘する
下痢して、残便感がある
赤い湿疹ができる
このような症状は、体内に熱がこもっている場合が多いです。
原因としては
ストレスで気の流れが悪くなっている。
辛いものの食べ好ぎ
羊肉やチョコレートなどの食べ過ぎ
便秘
血液の汚れ
などが考えられます。
治療としては、
清熱解毒薬 冷たいもので冷やすイメージ
滋陰清熱 水で冷やすイメージ
利気 発散 風で冷やすイメージ
瀉下 便秘を改善する
などです。
378.中医学ダイエット
中医学では、脂は痰湿の一部と考えます。
脂やお砂糖、水などが入り混じってドロドロになったものが痰湿です。
ですから、ダイエットを考える場合は、痰湿を考えます。
とりあえず痰湿をとる事は大切です。
ですが、もっと大切なのは痰湿がたまる原因を考えます。
例えば、脾虚の体質の場合は食べたものが栄養にならず痰湿になりやすい。
この場合は健脾消導の漢方を使います。
また、気の流れが悪い場合も痰湿がたまります。
血の汚れの瘀血が原因の場合もあります。
ですから、簡単にダイエットならこれという訳には行きません。
いろいろ体調が悪く、体質改善をしていくと自然に体重が減る事はよくあります。
しかし、体調がどこも悪くない場合、漢方的に見ても問題が無い場合もあります。
これは単純に食べ過ぎや運動不足です。
運動は薬の代わりになりますが、運動の代わりになる薬は無いと言われています。
ですから、漢方を飲むだけで手軽にダイエットできるというのは難しいと思われます。
377.色即是空
般若波羅蜜多経の中に、「色即是空、空即是色」という一文があります。
色と空の捉え方はいくつかあると思います。
私は、色は目に見える物、空は目に見えないが働きがあるもの、と考えています。
これは中医学に当てはめると、色は物であり、陰です。空は働きであり、陽です。
そうすると、この一文は、陰は陽であり、陽は陰である。つまり陰と陽は別々のようで同じものだという意味になります。
中医学ではこれを陰陽転化と言います。
陰は陽に変化するし、陽も陰に変化すると考えます。
働きを「エネルギー」と考えれば、物質はエネルギーであり、エネルギーは物質である、という意味になります。
これはアインシュタインの相対性理論そのものです。
何千年も前に、物質がエネルギーになり、エネルギーが物質になると解ったというのはすごい事ですね。
さらに中医学では、陰と陽はお互いに助け合い、制御しあい、バランスを保っていると考えます。
中医学の理論の中で一番重要な理論がこの陰と陽の理論です。
376.従化学説
中医学には、「従化」という概念がある。
同じ邪気を受けても、体質の違いにより症状が変化するという考え方だ。
例えば、同じウイルスや菌に感染しても、人によって少しずつ症状が違う。
これは、体内に入り込んだ邪気が体質によって変化したと考える。
これを「従化」という。
体質に従って変化したという意味だ。
治療方法も同じではない。
もともとの邪気は同じでも、従化によって症状が変化しているのでそれにあった治療方法を使う必要がある。
同じ風邪でも、鼻が悪くなりやすい人、喉が痛くなりやすい人、咳が出やすい人などがある。
それぞれ、使う漢方薬は違ってくるのだ。
だから、中医学では風邪なら葛根湯という考えは成立しない。
375.中国語のダジャレ
日本語にもダジャレは多いが、中国語もとても多い。
日本のダジャレは使い捨てだが、中国語のダジャレの名作は語彙として残る。
代表的なのが「気管炎」と、「粉丝」だ。
「気管炎」は日本語の気管支炎の意味だが、「妻管厳」の発音に近い。
妻管厳は、その文字のとおり、妻の管理が厳しい。
日本語では「妻の尻に敷かれている」みたいなイメージ。
「今日、飲みに行かない?」
「僕は気管支炎だから行かないよ。ゴホゴホ(ウソ咳)」
粉丝はもともとハルサメの意味だが、発音は「ふぁんすー」で、英語の「ファン」の複数形の発音に近い。
なので、「私はあなたのハルサメです。」と言われたら、「私はあなたのファンです。」の意味になる。
次のページ

トップページに戻る